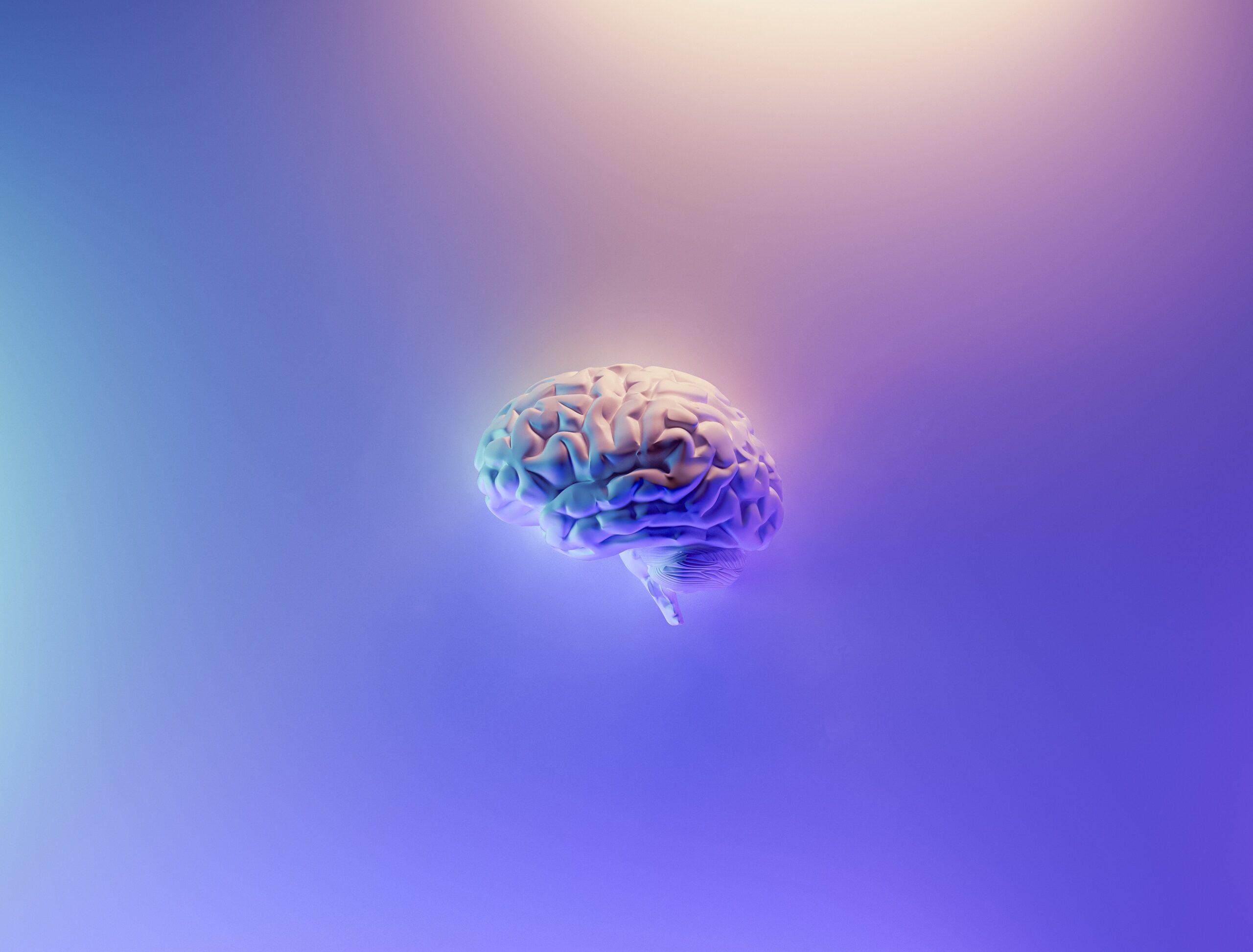保険関連の記事を制作したいけれど、専門的な情報をわかりやすく解説するのが難しい、コンプライアンス面で問題がないか気になる、といった悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、記事を制作したものの検索順位がなかなか上がらないといった課題もあるかもしれません。
本記事では、保険分野の記事制作でよくある課題に対応した、記事制作の方法やポイントを解説します。また、適切な外注先の決め方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
保険分野の記事制作の課題
保険分野の記事制作においてよくある課題として、次のようなものがあげられます。
- SEO対策をしても検索順位がなかなか上がらない
- 保険の情報を読み解いて解説するのは難しい
- コンプライアンスの問題がないか確認が必要
これらの課題に対処する方法とともに、それぞれ詳しく解説します。
SEO対策をしても検索順位がなかなか上がらない
保険というテーマは、SEOにおいて競争が激しく、多くのWebサイトが上位表示を狙っています。そのため、記事を制作したもののなかなか表示順位が上がらないという課題にぶつかりがちです。
また、保険は専門性が求められるテーマでもあります。Googleなどの検索エンジンは、より専門性が高く、信頼できる情報を上位に表示する傾向があります。
SEOで上位表示を達成するためには、単にキーワードを盛り込むだけでなく、読者の検索意図を深く理解し、有益な情報をわかりやすく提供しなければなりません。また、関連性の高い共起語を自然な形で記事に含めることで、検索エンジンからの評価を高められます。
保険の情報を読み解いて解説するのは難しい
保険商品は複雑なものが多く、専門用語も頻繁に登場します。それらを一般の読者向けに分かりやすく解説するのが難しいと感じることも多いでしょう。
読者にとって分かりやすい記事を作成するには、まず、筆者が保険についてしっかり理解している必要があります。専門知識がない人が記事を作成すると、内容がわかりにくくなるだけでなく、誤った情報を伝えてしまう恐れがあります。
保険の記事制作を外注する場合は、最初に関連する制度や用語のすり合わせを行うことをおすすめします。また、自社の商品についてパンフレットや契約書を読み込んでもらい、不明点を洗い出して解決することで、お互いに知識を深めると良いでしょう。
難しい専門用語をできる限り使わず、日常的な言葉で説明することも大切です。図やイラスト、表などを活用して、視覚的に分かりやすくするのも効果的でしょう。
コンプライアンスの問題がないか確認が必要
保険分野の記事制作では特に、コンプライアンス(法令遵守)が重要です。保険商品は金融商品の一種であり、不正確な情報や誤解を招く表現を使用すると、法律に抵触する恐れがあるためです。
例えば、保険商品のメリットばかりを強調してデメリットを隠すことや、将来の利益を保証するといった断定的な表現を使用することは、金融商品取引法や保険業法で禁止されています。
コンプライアンスの問題をなくすためには、記事の内容を弁護士や金融の専門家に確認してもらうのがおすすめです。また、記事中には必ず「免責事項」を記載し、記事の内容に基づいて行動した結果について責任を負わない旨を明記する必要があります。
さらに、記事の内容が最新の情報に基づいていることを定期的に確認し、古い情報や誤った情報が含まれている場合は都度更新・修正することも大切です。特に、関連分野で新たな法令の施行や既存の法令の改定があった際には注意が必要です。
以上のように、保険分野での記事制作においては、常にコンプライアンスを意識しましょう。
保険分野の記事制作のポイント
前述の課題も踏まえ、保険分野の記事を制作する際には、次のポイントを押さえましょう。
- 専門の制作会社に依頼する
- 専門家の監修を付ける
- クレジットを掲載する
- 引用・出典情報を掲載する
それぞれ詳しく解説します。
専門の制作会社に依頼する
保険に関する記事制作は、保険の専門知識がある記事制作会社に依頼するのがおすすめです。
保険業界の制度や規制、最新動向などを分かりやすく解説するためには、専門知識が求められます。また、保険分野はSEOの競争が激しい上に、法規制やコンプライアンスが厳格であるため、記事の品質を確保するためには専門の知見が必須です。
十分な専門知識を持つ制作会社に依頼することで、企画から執筆、編集、校正まで記事制作の全てのプロセスを安心して任せることができ、読者に有益で正確な情報を提供できます。
専門家の監修を付ける
保険に関する記事制作では、専門家の監修を付けましょう。
専門家とは、ファイナンシャルプランナー(FP)、保険募集人、弁護士、税理士など、保険や金融に関する専門知識を持つ人のことを指します。記事の内容に応じて最適な専門家に監修を依頼しましょう。
専門家の監修があることで、記事の正確性の担保、誤解を招く表現の回避、最新の法規制への適合を保証でき、読者に信頼感を与えることができます。
クレジットを掲載する
保険に関する記事には、執筆者や監修者のクレジットを掲載しましょう。クレジットには、執筆者や監修者の氏名、肩書き、所属先などを記載します。
誰が書き、誰が監修したのかを把握できることで、記事の信頼性が高まり、読者から参考になる情報と判断してもらえます。さらに、簡単なプロフィールや専門分野なども記載できると、より信頼性が高まるでしょう。
引用・出典情報を掲載する
保険に関する記事で使用したデータや統計、専門家の意見、法律や判例などには、引用・出典情報を掲載しましょう。
その際、引用・出典に該当する箇所に脚注や参考文献番号などを付与し、読者が簡単に情報源にアクセスできるようにしましょう。
引用・出典情報により、記事の内容が信頼できる情報源に基づいているとがわかれば、読者は安心して記事の内容を参考にできます。
保険分野の記事制作に適した資格
保険分野の記事を制作する場合に、向いている資格は次のとおりです。
- FP(ファイナンシャルプランナー)
- 生命保険募集人資格
- 損害保険募集人資格
これらの資格を持つ人が記事制作をすることで、保険に関する知識を求める読者に対して、有益な情報を提供できるでしょう。以下にそれぞれ詳しく解説します。
FP(ファイナンシャルプランナー)
FPは、金融や税金、不動産、保険など、幅広い知識を持ち、顧客のライフプランに合わせた資産設計をサポートする専門家です。
FP資格を持つ人は、保険に関する深い知識はもちろんのこと、顧客のニーズを理解し、最適な保険商品を選択する能力にも長けています。その能力は、記事制作にも活きるでしょう。
また、FP資格は、金融業界での信頼性も高く、記事の信頼性を高める効果も期待できます。
生命保険募集人資格
生命保険募集人資格は、生命保険の販売や勧誘に必要な資格で、保険会社や保険代理店などで働く人が取得しています。この資格を持つ人は、生命保険に関する専門的な知識を持ち、保険商品の仕組みや保障内容、税制などを理解しています。
生命保険募集人資格を持つ人が記事を制作することで、生命保険に関する正確な情報を提供できます。業界の最新動向や顧客のニーズなども、記事制作に活かせるでしょう。
損害保険募集人資格
損害保険募集人資格は、損害保険の販売や勧誘に必要な資格です。この資格を持つ人は、自動車保険や火災保険、地震保険など、損害保険の専門的な知識に加えて、保険商品の仕組みや保障内容、免責事項などに関する知識を有しています。
損害保険募集人資格を持つ人が記事を制作することで、損害保険の正確な情報を提供できます。業界の最新動向や顧客のニーズなども、記事に活かせるでしょう。
SEOに配慮した保険の記事制作の流れ
SEOを意識した記事制作を行う場合、次のような流れになります。これは、保険分野の記事以外にも共通する流れです。
- KWの調査・選定
- 構成案の作成
- 本文の執筆
- 校正・校閲および監修
それぞれ詳しく解説します。
1.KWの調査・選定
SEOを意識した保険の記事制作では、最初にキーワード(KW)の調査・選定を行います。
キーワード調査では、読者がどのような言葉で検索するのかを予測します。
まず、関連キーワードに対し、Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを活用して、検索ボリュームや競合性を調べましょう。メインキーワードを選定したら、サブキーワードや共起語も洗い出し、記事全体のテーマを明確にします。
例えば、「保険、記事制作」というメインキーワードであれば、「課題」「ポイント」などのサブキーワード、「SEO」「コンプライアンス」「専門家」などの共起語を組み合わせることで、より網羅的な記事を作成できます。
2.構成案の作成
キーワードを選定したら、そのキーワードを基に構成案を作成します。
構成案は、記事全体の設計図のようなもので、見出しや小見出し、各セクションで記述する内容などを具体的に定めます。構成案があることで記事の全体像を把握でき、一貫性のある記事を作成しやすくなるでしょう。
また、キーワードに関する読者の検索意図を反映することも重要です。例えば、「保険、記事制作」というキーワードで検索する読者は、保険分野の記事の作り方を知りたいはずです。
そのために、構成案には記事の目的やターゲットとなる読者、記事全体の流れ、各セクションで伝えるメッセージなども明確に記載します。
3.本文の執筆
構成案が完成したら、いよいよ本文を執筆します。構成案に沿って、各セクションの内容を具体的に記述していきましょう。
大切なのは、読者にとってわかりやすく、読みやすい文章にすることです。専門用語はできるだけ簡単な言葉で言い換え、必要に応じて図やイラスト、表、脚注などを活用します。記事のトーン・マナーを統一することも、読みやすさのために大切です。
また、SEO対策も意識しながら、キーワードを自然な形で記事に含めましょう。ただし、キーワードを詰め込みすぎると、読みにくい文章になるため注意が必要です。
4.校正・校閲および監修
本文が完成したら、最後に校正・監修を行います。
校正では、誤字脱字や文法ミスがないかなど、表記の正確性をチェックします。校閲では、記事の内容に誤りや誤解を招く表現がないかなどをチェックします。
さらに監修により、記事の正確性を専門家の目からチェックし、最新の法規制に適合していることを確認してもらいます。
校正・校閲および監修によって記事の品質を向上させることで、読者からの信頼性が高まるはずです。特に、保険に関する記事は、法律や税制など、専門的な知識が必要となるため、専門家による監修は必須と言えるでしょう。
記事制作の外注先を決めるポイント3つ
保険分野の記事制作を外注する場合、外注先を決めるポイントは次の3つです。
- 保険・金融分野の実績があるか
- アフターフォローが受けられるか
- コミュニケーションがスムーズに取れるか
それぞれ詳しく解説します。
保険・金融分野の実績があるか
保険や金融に関する記事は、専門的な知識や業界の動向に対する深い理解が欠かせません。
実績のある制作会社は、過去の制作事例や顧客からの評価などを提示できます。制作会社のWebサイトやポートフォリオを確認し、保険・金融関連の記事制作実績をチェックしましょう。
実績が豊富な制作会社なら、キーワード選定から記事構成、執筆、SEO対策まで、一貫して質の高いサービスを提供できる可能性が高いでしょう。
アフターフォローが受けられるか
記事制作は公開したら完了ではなく、公開後も、効果測定や改善策の実施、コンテンツのアップデートなど、継続的な対応が必要になります。
アフターフォローが充実している制作会社なら、記事公開後も効果測定や改善提案、コンテンツのアップデートなどをサポートしてくれます。
アフターフォローの内容や期間、料金などを事前に確認し、自社のニーズに合ったサービスを提供する制作会社を選びましょう。
保険分野での記事制作では、定期的なレポートや打ち合わせなどを通じて、制作会社と密接なコミュニケーションを取り、記事の効果を最大化できるよう務めてください。
コミュニケーションがスムーズに取れるか
記事制作は、企画段階から納品まで、制作会社と密接な連携が必要になります。そのため、コミュニケーションがスムーズかどうかは、記事の品質や制作期間に大きく影響します。
レスポンスの速さや担当者の知識や経験、提案力などを確認し、コミュニケーションが取りやすい制作会社を選びましょう。
また、打ち合わせや連絡手段などにおいて、自社に合った方法でコミュニケーションが取れるかも確認しましょう。
保険分野の記事制作ならNobol
本記事では、保険分野の記事制作の方法や課題、制作のポイントを解説しました。
保険分野では、SEOの順位が上がりにくい、保険に関する専門的な情報をわかりやすく解説するのが難しいといった課題があります。
こういった課題をクリアするためには、専門性の高い制作会社に記事制作を依頼したり、専門家の監修を付けたりするなど、いくつかのポイントがあります。監修を付ける場合は、FPや生命保険・損害保険募集人資格取得者に依頼しましょう。
株式会社Nobolでも、保険分野の記事制作に対応しています。
弊社では、マネー系ライターに登録された厳選されたプロのライターによって、高品質な記事制作が可能です。また、自社でのオウンドメディア実績を基に、ノウハウを詰め込んだメディア制作にも対応できます。
保険分野の記事制作にお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
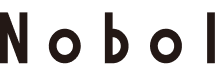
 2025年4月16日
2025年4月16日