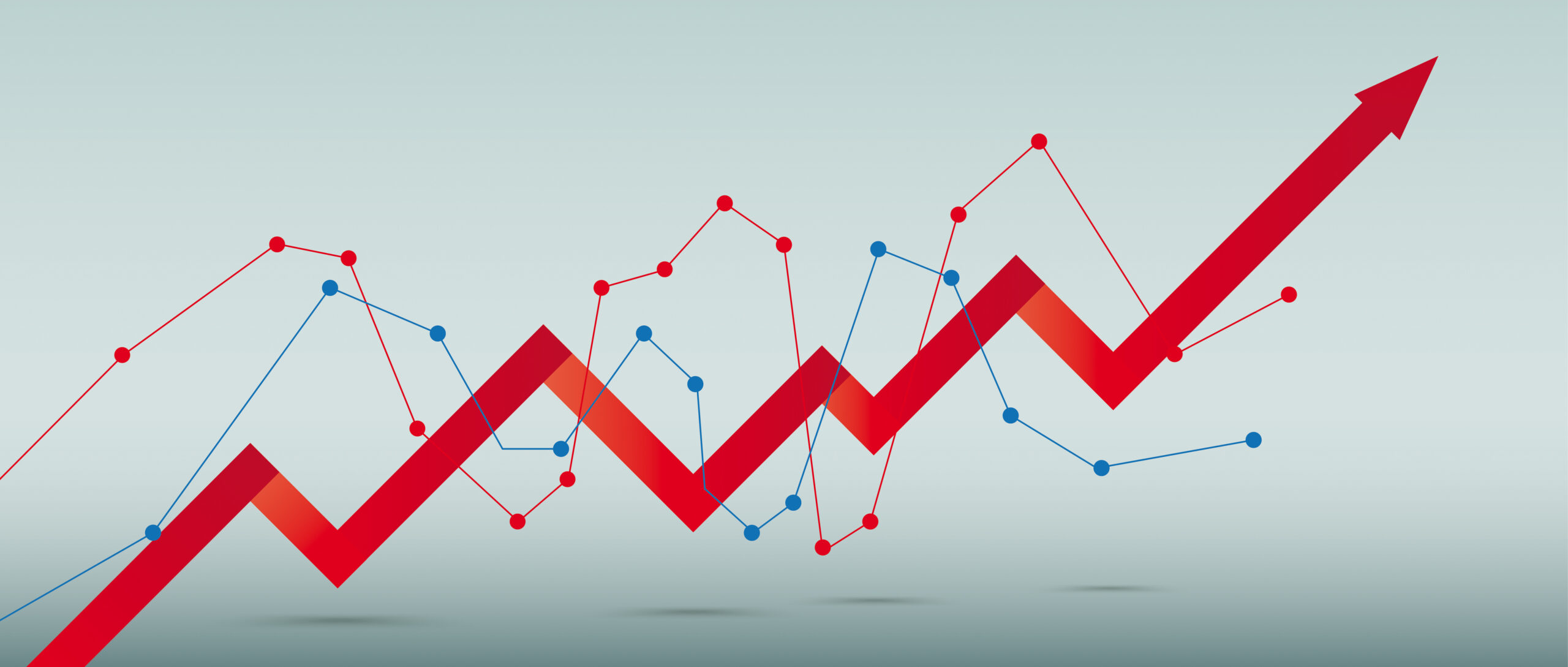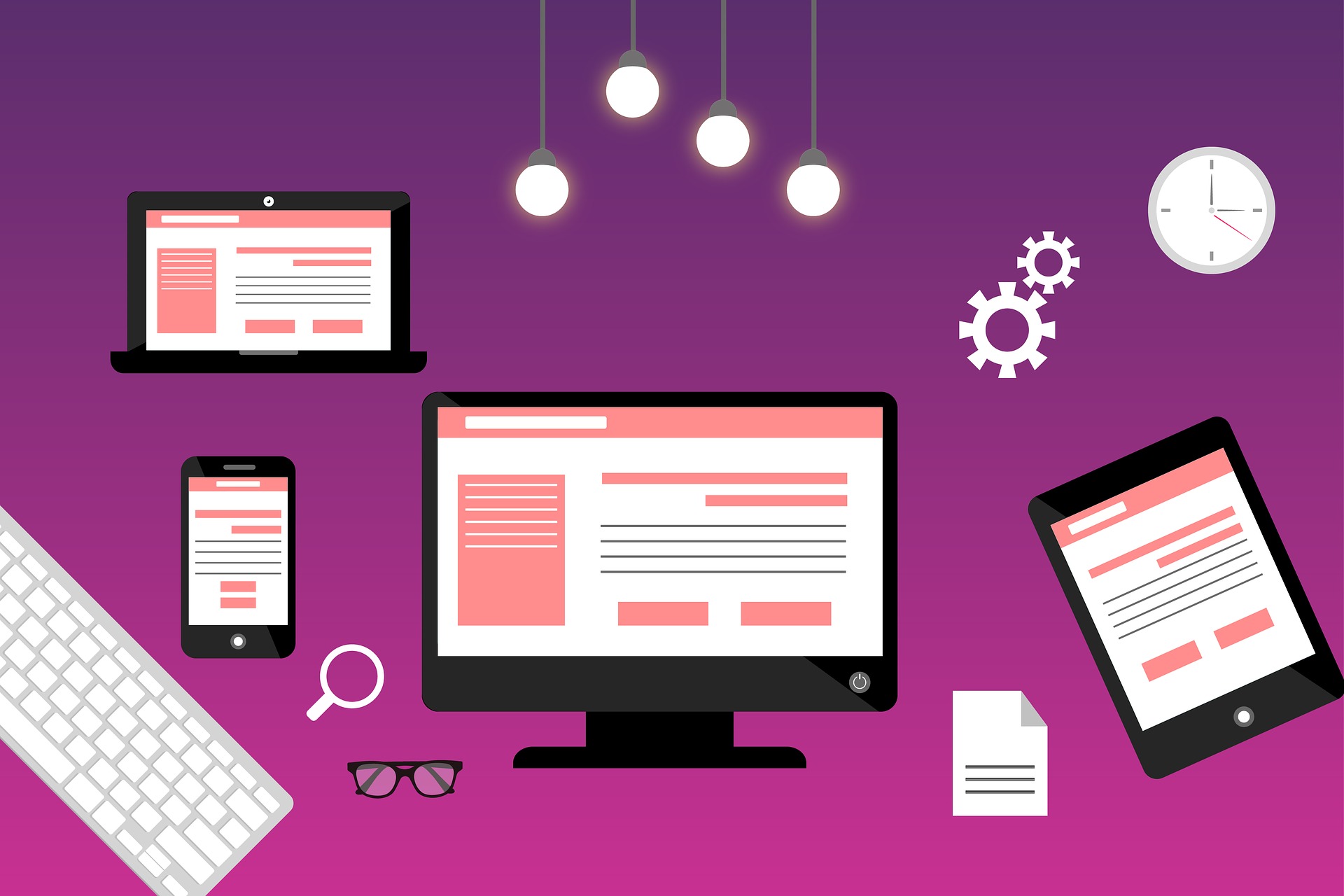編集の河村です。
BtoBの商材を扱う企業の記事制作において、どんな情報を発信したら良いかわからないというときに、おすすめするコンテンツのひとつが事例記事です。事例記事は、何らかの製品・サービスの導入を検討する企業担当者からつねに一定のニーズがあるコンテンツだからです。
BtoBの事例記事で成果を出すには、事例を読んだ企業担当者に、この製品・サービスを導入することで自社の課題も解決できるかもと感じられる内容であることが重要です。
また、事例として情報提供に協力してくれた既存顧客にもメリットを提示できると、事例の数やパターンが増え、より多くの潜在顧客の興味を引くことができるでしょう。
では、具体的にどうすれば良いのか。事例記事制作の流れに沿ってポイントをまとめてみます。
訴求ポイントに適した事例を選定する
事例記事を制作するには、まず、記事として紹介したい事例を選び、その事例の顧客に許可を取る必要があります。
事例選定の基準
事例なら何でも良いわけではなく、求める成果につながりやすい事例を選ぶことが重要です。基準としては、以下のような点があげられます。
- 訴求したい製品・サービスを利用中
- 導入前の課題や導入後の成果が訴求したい点に合致している
- 業態業種や規模感がターゲットとする層に合致している
事例記事のストックが少ない段階では、長年付き合いがあったり営業と親しかったりなど、頼みやすい顧客から声をかけるのもひとつの手です。
事例記事の数がある程度貯まってくると、参考記事として提示できますし、日頃あまりやり取りがない顧客にも頼みやすく、引き受けてもらいやすくなるはずです。
事例企業にメリットも提示する
事例記事に協力してもらう顧客企業には、取材や記事チェックのためにわざわざ時間や人手を割いてもらうことになります。
顧客企業にとってで負担の少ない時期や方法を選んだ上で、記事内で顧客企業のアピールポイントも載せるなど、協力のメリットがある形を心がけましょう。
また、インタビューと同時に、製品・サービスを利用するなかでの不明点や要望などをヒアリングする時間を設けるのもおすすめです。
訴求したいことを話してもらうために
取材先に事例記事として効果的な内容を話してもらうためには、事前の準備と当日の調整が重要です。
事前準備のポイント
事例記事を制作するにあたっては、記事の構成と質問事項について全体に共通するフォーマットを作成して、そのフォーマットを基本に事例ごとに必要に応じてアレンジする形をおすすめします。
事例記事を読む企業担当者は、自社と状況や課題が似ているものを何記事か読み比べらることが多く、記事ごとに構成や質問事項にバラつきがありすぎると、事例として参考にしづらくなるからです。
また質問事項は、余裕をもってあらかじめ取材先企業に共有しましょう。それにより、確認が必要なデータなどを当日までに用意してもらうことができ、取材がスムーズに進みます。
製品・サービスの訴求と事例のリアルさのバランス
事例記事では、製品・サービスの導入メリットについてターゲットにしっかりと訴求しつつ、良いことばかりでわざとらしいと読者に感じられないようバランスを意識する必要があります。
そのため、導入メリットを妨げない程度に、以下のような内容も入れると良いでしょう。
- 導入にあたっての懸念点と対応
- 導入時につまずい点と対応
- 担当者同士のやり取りや印象的なエピソード
- 今後の要望、改善してほしい点
記事を読んだ企業担当者に、製品・サービスの利用企業としてリアルな話だなと思ってもらえるような記事を目指します。
事例記事は集客だけでなく営業や開発にも役立つ
事例記事は、それを読んだ潜在顧客に問い合わせなどのアクションをしてもらうことを目的に制作されることが多いものです。
ただそれだけでなく、事例記事の数とバリエーションが増えることで、顧客に提案をする際にその実施イメージとして事例記事を提示できるようになります。
また、事例取材のなかで製品・サービスに関するヒアリングも行うことで、製品・サービスの改善や新たな開発にもつながるでしょう。
そういった点でも、事例記事は記事制作においておすすめしたいコンテンツといえます。
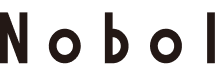
 2025年3月10日
2025年3月10日 2025年4月4日
2025年4月4日