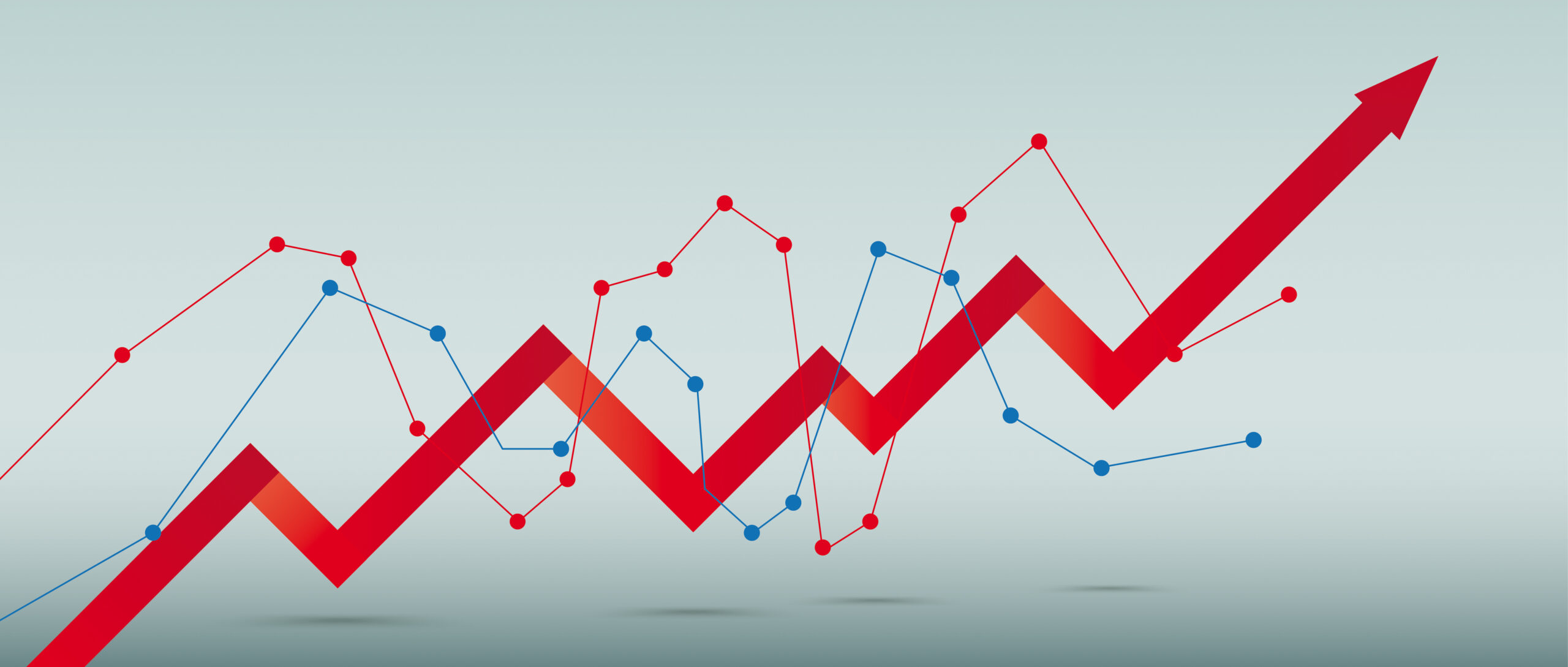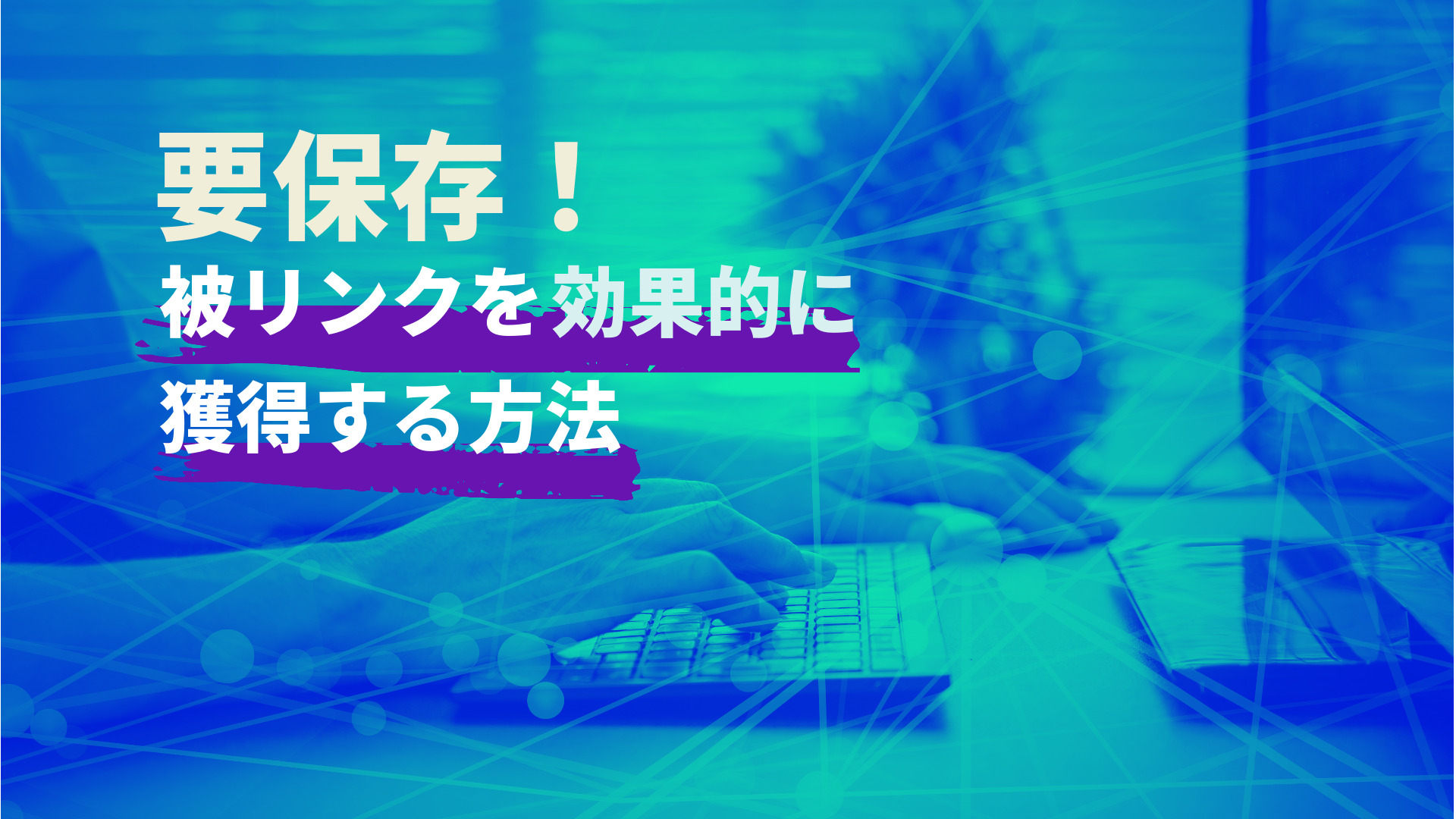編集の河村です。
記事制作に携わっていると、せっかく良い記事があるのに集客や拡散がうまくいっておらず、成果につながっていないというケースを目にすることがあります。
記事制作は、記事を制作したら終わりではありません。良い記事を制作することはもちろんですが、それを活かすには、記事の目標に応じた方法で集客や拡散のための働きかけが必要です。
ただ最近では、これまで定番だった記事の集客・拡散の方法に変化が生じつつあり、何に注力すれば良いのかわからないという声も聞きます。
記事の集客・拡散のための定番の方法と変化
記事の集客・拡散のための従来の定番としては、以下のような方法があります。なお、ここではWeb記事を想定しています。
- SEO
- Web広告
- メルマガ
- LINE
- SNS
SEOだけに頼るリスクが高くなっている
これまで記事の集客にはまずSEOといわれていました。特に、自社のことをまだ知らないものの、商品・サービスに興味を持ってくれる可能性が高い潜在顧客への情報発信にはSEOが効果的です。
しかし、生成AIの登場により状況に変化が見られます。ネット上で調べものをする際、検索エンジンではなくChatGPTなどの対話型AIツールを使ったり、Goole検索をしても検索結果上部に表示されるAIによる要約を見て済まされたりするケースが出てきています。
とはいえ、SEOが不要になっているわけではありません。SEOの要点を押さえた記事を制作することは、読み手にとって有益な記事を制作することになるからです。
しかし、集客をSEOだけに頼ることのリスクは上がっているといえます。
また、記事の内容についてもこれまで以上に独自性や専門性、読み物としての興味深さが求められるようになるでしょう。この辺りのことは以下の記事で詳しく触れています。
なお、検索内容に応じた広告が表示されるリスティング広告についても同様のことが言えます。
メルマガ・LINEは状況に応じて両輪での運用を検討
メールマガジンは、既存顧客への情報発信に効果的な方法とされてきました。
しかし最近では、日常の連絡ツールとしてメールではなくLINEやSNSが主流になり、ビジネスの連絡でもSlackやChatworkなどのチャットツールの活用頻度が上がっています。
そのため、メルマガは効果が薄れているといわれることもありますが、メールがまったく使われなくなっているわけではありません。ネット通販やWeb上のサービス利用ではメールアドレスが必要ですし、ビジネスではメールは依然として主要な連絡ツールのひとつです。
どちらかというと、かつてはオンラインの連絡手段がメール一本だったところから、連絡手段が多様化しているといえます。
そのため、既存顧客へのアプローチも、自社の顧客層とそのニーズに応じてメルマガとLINEの両方、場合によってはそれ以外のツールも含み検討したほうが良いといえるでしょう。
連絡ツールが複数になる場合、運用に工数がかかりすぎないよう、一元管理できるツールも合わせて活用することをおすすめします。
SNSはプラットフォームの運営方針や規約の変化を捉え、複数の選択肢を持つ
近年主流のSNSとしては以下があげられます。プラットフォームごとの特徴を踏まえたユーザーに情報発信ができ、ブランド育成やファン育成にも効果的な方法です。
- X(Twitter):拡散力が高い。幅広い年齢・性別のユーザーがいる
- Instagram:画像ベースでのブランド・ファン育成に効果的。ネット通販と相性が良い
- Facebook:ビジネス利用が多い。ユーザーの年齢層が高め
- TikTok:拡散力が高い。若い世代のユーザーが多い。ライブコマース利用もされている
ただし、SNSはプラットフォームの運営方針や規約の変化により、情報発信の効果やユーザー層が急速かつ大きく変化することがあります。今、まさにその変化が起こりつつあるといえます。
情報発信をひとつのSNSに頼り切っていると、一気に集客力がなくなったり、ブランドを毀損するというリスクもあります。
また、たとえばblueskyなど上記以外のSNSの利用も増えています。ひとつのSNSですべての情報収集や発信を行うのではなく、目的や情報の種類に応じてSNSを使い分けもされている印象です。
そういった変化に対応するために、自社のユーザー層やそのニーズを鑑みつつ、複数のSNSで並行して情報発信を検討してみると良いのではないでしょうか。その際、複数のSNSでの投稿を連携できるツールや、投稿フローを定めておくことで運営を効率化できます。
また、生成AIの登場により、SNS上に投稿したデータの権利が守られるのかという点も、プラットフォームごとに注意したいところです。
SNS運用担当者は、これまでこうだったから大丈夫と考えずに、各プラットフォームの運営方針や規約の変化について最新の情報を収集し、対応していく必要があるでしょう。
大前提として自社のサイトに情報を蓄積しておくことが大切
良い記事があっても集客や拡散がうまくいかないと成果につながらないと冒頭で書きましたが、逆に集客や拡散のためのプラットフォームやツールがあっても、発信すべき情報がないと何も始まりません。
自社でコントロールできる自社のサイトに良質な記事を蓄積しておけば、外部のプラットフォームやツールに何かあったとしても、大元となる情報が失われることはありません。変化に対応しながら、その点は忘れずに良質な記事制作を継続していくことが大切です。
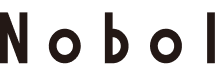
 2025年3月24日
2025年3月24日