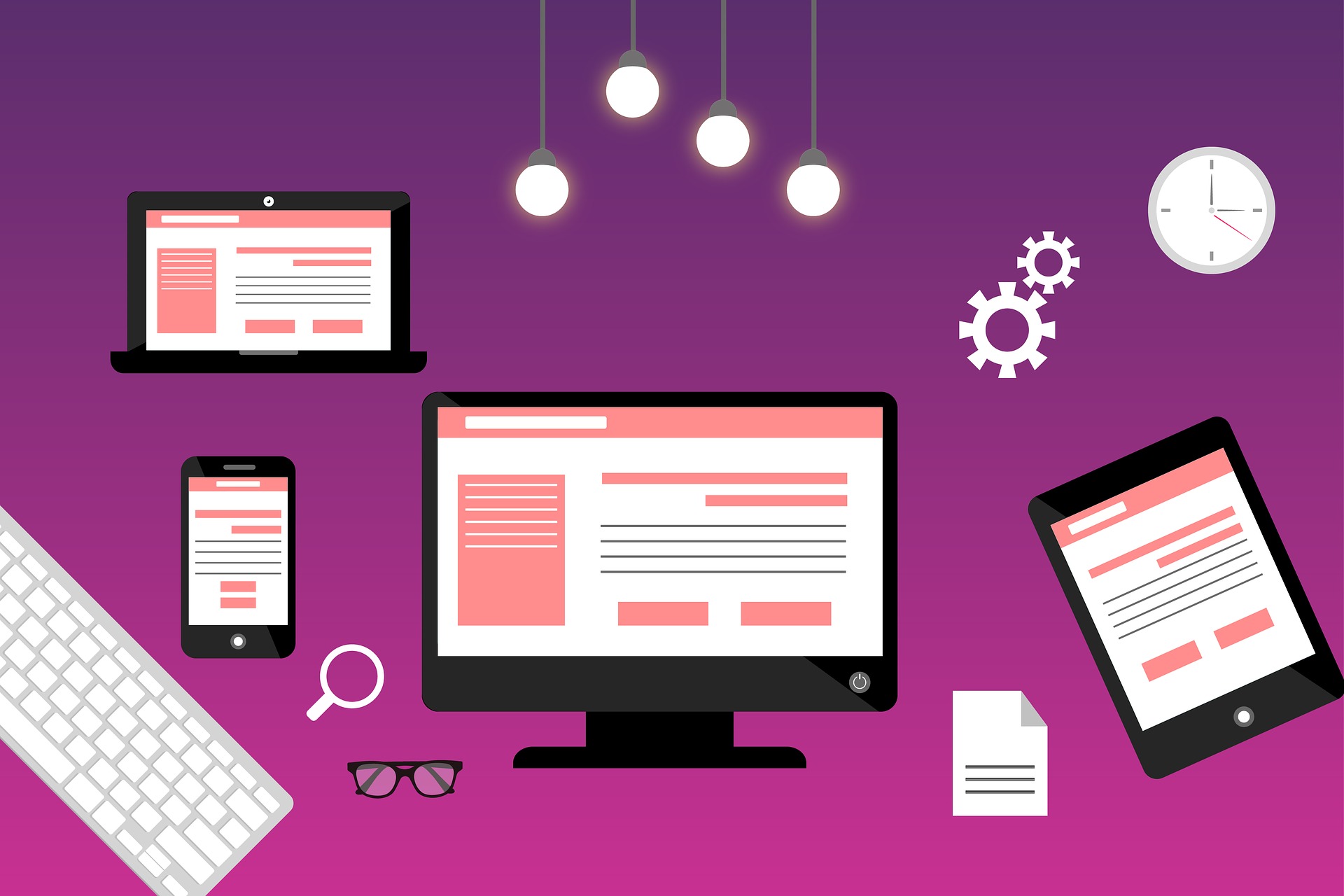編集の河村です。
企業の記事制作は、多くの場合、マーケティング施策の一環として行われます。
マーケティング施策の実施や継続を判断するために重要なのが費用対効果です。最低でもかかったコスト以上の成果を出し、できるだけ費用対効果を高くする必要があります。
では、記事制作の成果やコストはどのように測れば良いのでしょうか。
記事制作の成果を測る指標と目標設定
企業の記事制作の目標としてわかりやすいのが、記事経由で獲得したCV数です。CVに設定するものとしては、以下のようなものがあります。
- 会員登録
- 資料DL・請求
- ウェビナー・セミナー・イベント等の参加申込
- 問い合わせ
- 商談申込
- 商品・サービス申込
特にBtoB商材や高単価のBtoC商材の場合、いきなり商品・サービス申込を狙うよりも、まずは会員登録や資料DL・請求など顧客にとってハードルの低い行動をCVとして設定して、見込み顧客獲得を狙うことが多くなります。
また、商品・サービスやブランド、会社の認知度向上などを目的とする場合、まずはWebサイトへの集客を増やすことを重視して、PV数を目標に設定することもあります。
記事制作にかかるコスト
記事制作を社内で行う場合、外部にお金を払う形でのコストはかかりませんが、社内の人的リソースを投入する必要があります。
その場合、記事制作に社内スタッフが何名必要で、それぞれ何時間稼働するのかを明確にしましょう。
記事制作においては、一般的に以下のような業務が発生します。特に★印は、記事の内容に関わらず必ず発生する業務です。
- 進行管理★
- 記事テーマ選定★
- 記事テーマに応じた調査★
- 構成案作成★
- 取材
- 撮影
- 執筆★
- 写真選定
- 画像作成
- 校正・校閲★
- CMS入稿★
記事制作を外注する場合は、その分の費用がかかります。どこまでの業務を依頼するかによって、費用は変動します。
記事制作会社によっても対応している範囲が異なるので、外注したい業務に対応しているかを最初に確認しましょう。記事制作会社に相談しているうちに、自社で対応できると思っていたけれど外注したほうがほうが良さそうという気づきもあるかもしれません。
費用対効果を測る
費用対効果を測る基本は、「効果ー費用」です。効果を売上など金額で示せる場合は、この式で費用対効果を算出できます。
ただし、記事制作では会員登録数やPV数など金額で表せない目標を設定することも多いため、「効果ー費用」で費用対効果を表すことは難しくなります。
その場合、効果を示すためには、目標設定とその達成度、実際にかかったコストを明確にして、効果検証を行いましょう。
また、過去のデータを基に、目標としている指標とその達成度から、どれくらいの売上につながる可能性があるのかを示せると、より費用対効果がわかりやすくなります。
たとえば会員登録数を目標に設定した場合、過去のデータから会員登録者のうち商談に進んだ割合と商談の成約率を算出して、記事によって獲得した会員数にそれをあてはめることでどのくらいの売上につながる可能性があるのかを計算できます。
記事制作の費用対効果は中長期的に見ることが重要
記事制作は、広告出稿のように実施したらすぐに売上につながるというものではありません。
たまたま1本の記事がバズって数字が伸びるということがないわけではありませんが、短くても3ヵ月~半年、できれば1年間くらいは様子を見るつもりで進めるほうが良いでしょう。記事本数が増えることで、Webサイト全体として効果が伸びてくる面もあります。
もちろん、その間ただ制作を続ければ良いというわけではなく、各記事およびWebサイト全体の効果検証を定期的に行い、改善を重ねていくことが重要です。
そのためにも、記事制作を行う前に目標と想定されるコストを明確にして、記事制作後に目標と想定に対して実際はどうだったのかをきちんと振り返れるようにしておく必要があります。
なお、記事制作会社によっては、記事を制作して納品するだけでなく、そういった効果検証までサポートしてくれるところもあります。
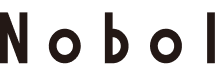
 2025年4月7日
2025年4月7日